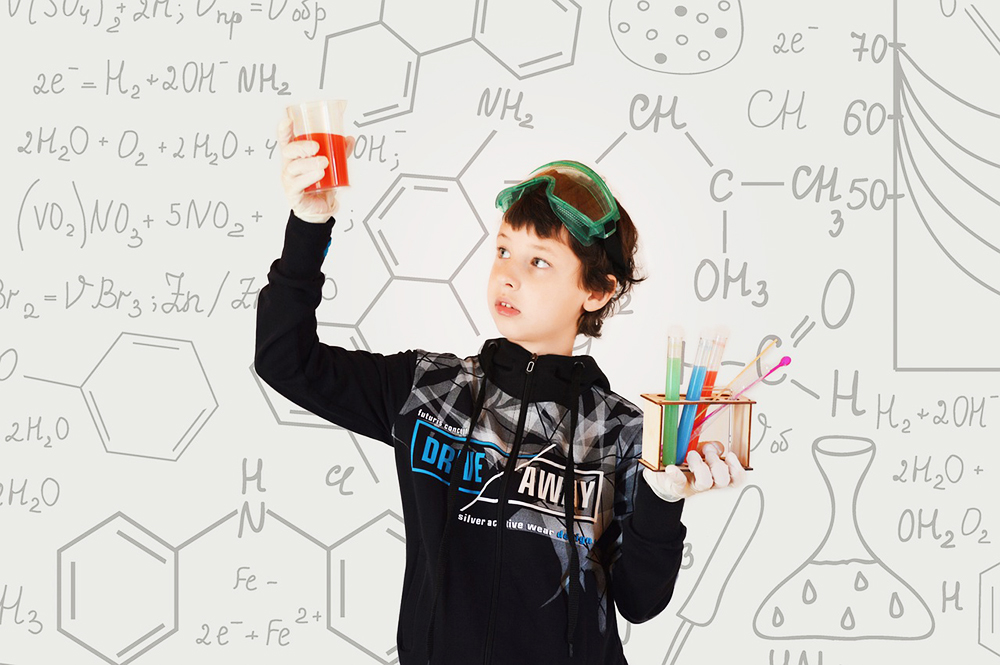米が酒に、土が器に(3)
丹波篠山では今西が土の仕込みを行っていた。昨年4月に夢前で採取した土は、今西の手により長い時間をかけて陶土に精製されていたのである。


採取した土は、余分な水分を取り除くために土嚢袋に入れた状態で数ヶ月寝かしておく。適度に水分が抜けると袋から取り出して、土塊を木槌で叩いて粉砕していくのだ。通常、粉砕する作業は機械で行うのであるが、今西は木槌を使い全て自らの手で細かく砕いていく。機械でやってしまうと良いものも悪いものも全て一緒になってしまうため、手作業で行うのが一番いいのだという。

山のように積み上げられた土嚢袋から土を取り出し、木槌で叩く。ピンポン球くらいの小石や異物が見つかれば取り除いていく。土塊を割ると稀に中が黒色の土が出てくることがあるが、これは鉄を多く含んだもので、釉薬にすると良い色が出るらしい。石や異物を取り除きながら、こうした使えそうな土も別にしておく。土を取り出しては砕き、選り分け、また砕く。このような地味な作業が延々と続けられるのだ。

粉砕した土はケースに入れて、上から水をかけて湿らせ、また寝かせる。数百キログラムから数トン分、今西は何日も何日もかけてこの地味な粉砕作業を行うのである。まだまだ陶土になるまでの入り口の工程に過ぎないのであるが、この時点で既に気が遠くなるような時間と手間をかけている。恐るべし、今西。


粉砕した土を今度は手で細かくほぐしていく。ほぐしながら、ここでもまた異物があれば取り除く。通常はふるいにかけて行う作業であるが、今西はここでも手を使う。ふるいで選別してしまうと必要なものまで取り除かれてしまうのだという。手に違和感を感じる異物を取り除きながら、指先に神経を集中させてほぐしていく。この方法が一番「土の再現性」があり、その土地そのものが器になった時に現れるのだと、今西は土と向き合いながら語るのであった。


手でほぐす作業も恐ろしく時間がかかる。まともな神経ではやっていられない。ふるいにかければすぐに終わるであろうに、今西はそれを選ばない。全ては良い作品を生み出すためである。
「どうやって(器を)あんな風に焼くんですか? って聞かれるんやけど、土こうして作ってこう やって準備したら、自然と焼く時に窯詰めとかめっちゃ考えるやん。そしたらできるで、ってい うことやねんけどな。」
今西がさらりと説明するその作業は、常人には到底できそうにない。機械化が進んでAI時代に突入しようとする現代において、時代を全力で大逆走して振り切って頂点を目指す男、それが今西である。土が入ったケースの前の小さな座布団に座って延々と土をほぐし続ける今西は、もはや常軌を逸している。このストイックという言葉では片付けられない極限の作業から、今西の作品は然びの境涯と魂を持って生まれるのだ。
土と向き合いながら今西は言った。
「これぐらいやらんかったら窯詰めて焼く気せーへんやろ!」
丹波篠山の片隅で、常人には理解し難い今西の陶芸ワールドがひっそりと炸裂している。

今西の手によってほぐされた土はまた寝かされる。このような多くの繊細な工程を経て、田んぼの土と山の土が混ぜ合わされて陶土となるのである。
最後に粘土の成分を均一になるようにして、土中の空気を抜く土練りを行う。しっかりと練ることで成形と焼成に耐えられる土に仕上げるのだ。土練りは足で踏んだり手で捏ねたり機械を使ったりと、その土の状態によって変えるのだが、今回の夢前の土は手で練ることになった。

まずは「荒練り」といって土を均一な軟らかさになるように練る。荒練りを終えた陶土はまた寝かせて、可塑(かそ)性(形を成形する際に自由に形を変える性質)を高める。次に陶土の気泡を抜いて焼成の際の破損を防ぐための「菊揉み」をする。練り終わった後の形がまるで菊の花のように見えることからその名が付いた練り方である。



リズミカルに素早く練り上げる今西。陶芸界では「土練り三年」という言葉があるように、練る作業は非常に難しい。陶芸家は長い年月をかけて体得しなければならないのだという。
「これええなあ、ええ土や。」
菊揉みをしながら今西は満足そうに呟いた。練ることで何かが分かるのであろう。夢前の土は 陶芸家の満足のいく仕上がりになりそうである。 菊揉みを終えた陶土は一晩寝かされる。これまで何度もされていたこの「寝かす」工程もただ 放っておくのではない。土は生きており、凍ったら駄目になってしまうものらしい。丹波の冬は非常に寒い。土のために室内の温度が下がらないようにストーブを焚きっぱなしにすることもあるようだ。
陶土を一つひとつ丁寧に毛布や布団でくるんでいく今西に、何故布団でくるむのか理由を尋ねると、彼はさも当然とでも言いたげな顔でこう答えた。
「え? だって寝る時って布団かけるやろ?」
今西にとって陶土は子どものようなものである。大事な我が子を布団にくるみ、愛情かけて育てることで、器には魂が宿るのであろう。

土を一晩寝かせた後、やっと轆轤(ろくろ)での成形となる。いよいよ酒器の形が作られるのだ。
轆轤の台に土を置き、回転させる。土の塊だったものが、今西が手指を当て、土を立ち上げては下ろし、また立ち上げて、と繰り返すうちに器の形になっていく。土から酒器となる瞬間である。回転する轆轤の前に座って簡単そうに作業を続けている今西であるが、この成形をまともにできるよう になるまで三年はかかるという。繊細な指の動きにはプロの陶芸家としての経験と情熱が込められているのだ。


今西は轆轤を回しながら呟いた。
「焼いたらこんな風になるやろなって感じが見えるような土やな。」
いい調子で出来上がりつつあるようだ。そんな今西をカメラで撮影すると、目をきらきらと輝かせ少年のようなとてもいい笑顔である。
こうして酒器の成形が無事終わった。後は窯に入れて焼くだけである。焼成の際には釉薬が必要となるが、飯塚は籾殻をうまく灰にすることができたのであろうか。果たして酒器はどのように仕上がるのであろうか──。それはこの時点では今西のみぞ知ることである。

(続く)