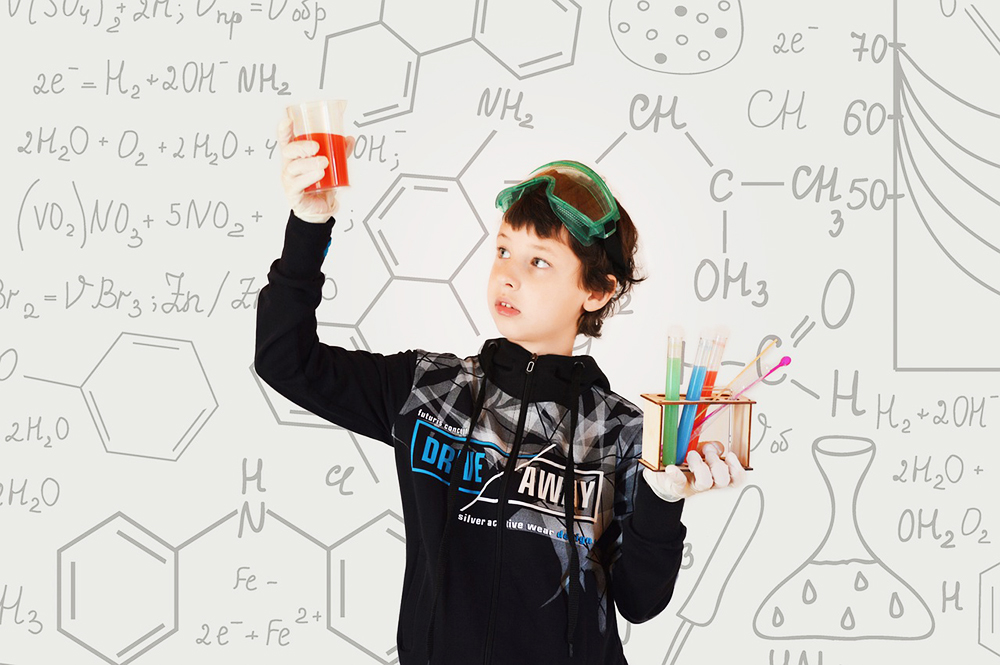藤布(ふじふ)

藤布(ふじふ)とは藤の蔓を細く剥いで糸を作り織り上げた布のこと。ざっくりとした素材で通気性の良さから、昔は夏衣の一つとして日常に使われていました。明治時代を迎え木綿の大量生産が可能になると同時に、藤布は衰退します。今では夏帯などで僅かに使用されるほど。藤布はいまやほとんど見ることができませんが、古来から近代まで日常使いに重宝されてきました。
藤布の歴史はとても古く、縄文から弥生時代には既に生産されていました。日本最古の歴史書といわれる古事記にも「春山之霞壮夫(ハルヤマノカスミオトコ)の母が、藤蔓から衣・袴・襪・沓を一夜で製織して与えた」と記されています。繊維が長く強いため、普段着はもちろん仕事着などでも活躍していたようです。
大君(おほきみ)の塩焼く海人(あま)の藤衣
なれはすれどもいやめづらしも
よみひとしらず
大君のために塩を焼く海人が来ている藤の衣のようにすっかり慣れきった人だけれども、ますます愛おしく思っています。
昭和期の作家・森田たまは衣がえについての一文を残しています。
「初夏の緑の下に初あわせの軽きをよろこび、六月一日からは寒かろうと暑かろうと単衣ものを着る。それが私たちの、母の時代祖母の時代からの約束であった。(中略)日本の着物の生命は柄や生地にあるのではなく、季節の約束を守るところにその真ずいがあるのであった。」
(森田たま「衣がえ」より)
衣服に対する考え方が令和に生きる私達の感覚とは随分離れていることに気付かされます。暑い寒いの気温の変化ではなく、もっと細やかな季節の移り変わりを服装に託していたのだと思うと、昔の人の感性にどうしたら追いつけるのだろうかと考えてしまうのです。